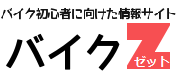多角経営による後発バイクメーカー
ヤマハ発動機はもともとは楽器製造からはじまったメーカーです。
ヤマハ発動機の前身は「日本楽器製造」という楽器製作と修理を行う企業でした。
日本楽器製造の創業者は山葉寅楠で、和歌山県に徳川藩士の息子として生まれたのちに長崎に出て時計作りを学び、のちに医療機器の修理業をしていたときにオルガン修理を依頼されます。
そこでオルガン修理だけでなく自らオリジナルのオルガンを作りたいという希望を持つようになり、4年後に「山葉風琴製造所」という会社を作り後に「日本楽器製造」と社名を変更します。
このオルガンづくりはのちに航空機用プロペラなど多角的な部品製造と販売を行う方向に発展し、ヤマハというブランドを多方面に広げていきます。
戦時中には軍需工場として大きく企業を発展させていきますが、戦後にもこの多角的な製造分野は意欲的に広げます。
そんな中で登場したのが「ヤマハ125」という初代バイクで、既に数多くのバイクメーカーが進出しているバイク市場において後発メーカーとして参入していったのです。
当時のポスターを見ると「次にお求めの際はYAMAHA125」といった控えめなキャッチフレーズがついているのが面白いところです。
楽器メーカーから日本第二位のバイクメーカーへ
発売当初には「楽器屋がつくるバイク」として世間から色物扱いをされていたようで、バイクショップに本体を置いてもらえずやむなく系列の楽器店でバイクを販売していたりしています。
しかしヤマハはもともと軍事用モーター品とともにピアノやオルガンという外装や塗装に非常に高い技術を要する産業を担ってきたこともあり、バイク製造でも次第に強みを発揮していくことになります。
ヤマハのバイクの特徴は美しいフォルムと基本性能の高さで、次第にシェアを伸ばしていくことでついに日本第二位のシェアを獲得するにいたります。
むしろ現在では「ヤマハ」と聞いた時に楽器製造よりもバイクメーカーとしての認知度が高くなっているほどで、もともと備えていた技術とバイク製造との相性が非常によかったということがうかがえます。
ホンダには一歩及ばない部分も否めませんがバイク性能の高さも多くのバイクファンが認めるところであり、時々とんでもない名車をリリースしてくるサプライズ感の大きいメーカーでもあります。
代表的な名車と言えばやはり「YZF-R1」「ドラッグスター400」という大型のバイクで、中でもYZF-R1は1998年に発売開始されてから独特の軽量の車体と「猫足」と言われている鋭い足回りとが日本だけでなく世界的にも人気となっています。
ヤマハの代表的なバイク「YZF-R1」ついて
ヤマハを代表するバイクであると同時にヤマハのバイク作りの思想をそのまま体現するものとなっているのが「YZF-R1」です。
YZF-R1はその前身として世界のモーターレースを圧巻したYZR-M1というスポーツバイクのレプリカ版として作られたもので、「サーキット最速」の走りを体験することができるバイクとして多くのファンを獲得しています。
R1の足元を表す言葉に「猫足」ということがあるのですが、これはコーナリングをするときにギャップをものともせずに走行できるという安定感を示すものとなっています。
またレース用にサスペンション性能を高く作られているので、レーシングタイプバイク独特の姿勢に慣れてしまうとかなり乗り心地よく過ごすことができます。